書いている人
フィンランドの教育系大学院を修了した2児の母
元小学校教員
エラスムス+制度を利用し、2024年春はドイツのUniversity of Regensburgにも留学
研究テーマは子どもの遊び環境
フィンランドに関する執筆・講演活動と英語指導を行っている
Kinaco
Contents
修論提出までのスケジュール感
修士1年目
私の所属するコースは、教育学部にありますが、Teacher Training とは異なり、科学的に教育に関する内容を研究するコースです。
よって、一年目の前期からリサーチの技法やプレゼンをする授業が開講されていました。
割と早い段階で修論セミナーが開講され、少しずつどんなことをしたいかを書いたり話したりしながらアイデアを進めていきました。
私はテーマが明確に決まっていたこともあり、先生も「それでやるんでしょ」という感じで興味を持ってくれていました。
ただ、テーマは決まっていたものの、それをどう具体的に研究という形にしていけばいいかが全くわかりませんでした。
自分の興味のあるテーマから、研究対象を実現可能なものに落とし込むまでに非常に時間がかかったといえます。
「絶対これを扱いたい!…でもどういう切り口からなら研究できるの?」とだいぶ長く悩んでいました。
また私の場合は、一年目の後期はドイツに交換留学にいっていましたので、修論の話は頭の隅に置かれた感じになってしまいました。
ただドイツでもプロジェクトワークを通して研究方法論を学ぶことができました。
実際、このときに仲間とやったインタビューと分析の経験が、自分の修論でも大いに役立ちました。
何がどこでどう役立つかわからないので、やっぱりどんなことでも興味を持って取り組んでおくのはとても大事
修士2年目 前期
修士二年目は現地小学校でのインターンシップが始まったこともあり、非常に忙しくなってしまいました。
昨年の先輩は2年目の最初にはデータ集めを始めていたし、他の先輩に聞いてみても、前期のうちに計画して書き始められるところからやっていたとのこと。
大きなきっかけなったのは、Scientific Writingのクラスでした。
修論の一部分を書いてみんなで読み合うというもの。なんとしても何かは持っていかなくてはいけません。
当時考えていたことを、むりやり絞り出してイントロダクションを書きました。
でもこれが結果的に良かった。
詳しくは後述しますが、頭の中でグルグル悩んでいても進まない
書かなきゃだめ
考えを練ってから書くのではなく、書きながら練るほうがいいと思う
結局このむりやり書いたイントロが思いの外評判がよく、先生からも仲間からも、ぜひこの続きを読みたいという意見をいただきました。
この授業がきっかけで、自分の研究の方向性に自信をもつことができ、そこからようやく次のステップに踏み出すことができました。
修士2年目 後期
提出期限の約半年前からインタビューの準備を開始。
並行して友人に声をかけまくり、英語でインタビューを受けてくれる人を探しました。
インタビュー設計ができたところで、インタビューを開始。
数名分溜まったところで分析開始。
とはいっても分析だってどうやっていいやら途方にくれるところから始まりました。
そもそもインタビューの書き起こしやコーディング、分析手法や個人情報の管理
一つひとつ聞いたり調べたりするしかありません。
このあたりも、研究の経験が少ない人は覚悟しておいたほうがいいかもしれません。
また、わたしの場合、途中で先生と相談してインタビュー数を増やすことになったりして、当初の計画より大幅に遅れることになりました。
計画通りにいかないなんてことは、あるある
このあたりも想定してゆとりをもった研究計画が大事
そして、提出前の最後の二ヶ月はほぼ執筆に集中。
もうデータも揃っていましたし、そのほかの授業もほぼ終了しており、完全なる引きこもり執筆期間になりました。
ときどき修論セミナーに顔を出して意見をいただきつつ、ひたすら書きまくりました
私はチャプターごとに書いたものを先生に提出してフィードバックをもらっていました。
それを反映させながら全体を仕上げ、体裁を整えて6月末に無事提出
…と、随分あっさり書いてしまいましたが…
実際は、ほーーーーーーーんとに進まない
わたしもWritingが特に苦手というわけでもなかったのに、まぁ苦しみました。
何時間もやってるのに、見返してみると、「あれ?書けたのこれだけ?」なんてことがしょっちゅうでした。
だけどね、研究を文章にまとめるって、そもそもそういうもの
修士の学生なんて、まだまだ研究ド素人のひよっこ
でも毎日毎日必死で取り組んだ、その「たったこれだけ?」がいくつも積み重なって、いつか修論という成果物
だから、自分の書けなさに落ち込んだとしても、諦めずに頑張ってほしいな
これから修論を書く予定の人に伝えたいこと
わかるから書くんじゃない、書くからわかるのだ
これから修論を書く方に、あるいは二年前の修士課程を始めた自分に、いま声を大にして伝えたいことがあります。
それは、
とにかく早く始めろ!
です。
いや、当たり前過ぎますね。
これ、もちろんわたしも、大学院入ったときから十分わかっていたんです。
わかってないわけないですよね。
普通、思いますよ。何万字の英語論文、早く始めないとヤバいぞって。
でもこれがなかなかできなかった。
ちなみに、決してサボっていたわけではありません。面倒くさくて進まなかったとかじゃ全然ないんです。
修論のことはずっと考えていましたよ
でも、これでいいのかずっと自信がもてなかった
だけどね、今終わってみて、すごくはっきり言えることがあります。
それは…
「わかったから書くんじゃない。書くからわかるのだ!
です。
うじうじしてないで、とりあえず手を動かして頭の考えを脳みそから引っ張り出したほうがいいです。
早い段階で、できれば文章にして、あるいはコンセプトマップでもいいかもしれない、周りに見てもらえる形にする
そうすれば、まとまらないアイデアであっても、先生だってアドバイスすることができます。
具体的にはこんなこと…
問題意識やリサーチクエスチョンは、まずは自分の思いでいいから文章にしておく
とりあえずイントロダクションを書いてみて面白そうな研究か検討してみ
Methodologyはやり始めたところで計画書代わりに文章にしておく
結果が揃うまで待つのではなく、とりあえず書けるところから書く
データを集めながら分析を始める
書くことは科学的思考のトレーニングになる
この2年間を振り返って、修論を早く始めるべきだったと思う理由はもう一つあります。
それは、もっと早い段階から論文執筆に実際に取り組んでいれば、大学院中の論文の読み方も随分変わっただろうな
私は論文を読むのは基本的に好きなのですが、振り返るとまだまだ読めていなかったなと思うのです。
どういう順番で書いただろうか、論文の中でもどこがポイントになるのだろうか、そもそも何を知りたくてこの研究に取り組んだんだろうか、この手法で本当にわかるのだろうか、etc…
これって要はCritical reading
実際に自分が研究というものをやってみたあとでは、批判的に考察できる力が確実に付いた気がする
科学的思考って、受け身でいる段階では、まだ熟成されないんでしょうね
研究者ってこれをその経歴の中で何度も繰り返すことで、科学的に物事をみる訓練をしてきた方たち
今まで読んできた論文も、修論を終えた今読み返したらきっと気づくことが違うんだろうなって思います。
だから、ぜひ修論に早めに取り組んで、在学中から科学的思考を少しでも伸ばしておくと、グッと有意義になるんじゃないかなと思います。
修論を書き終えて、いま思うこと
正直にいって、修論を仕上げることは、私にとっては非常にチャレンジングでした。
つまり、めちゃくちゃ大変だったんです。
「人間の頭って、ほんとにいつか爆発するんじゃないかな」って思うくらいには、頭を使ったと思います。
フィンランド人の友人なんかは、「スケジュールも安定していたし、卒論に比べて楽だったよ」なんて苦しんでいる私の前で笑顔で話す猛者もいましたけどね。
まぁ経験も実力もないんだから仕方ない話です。
でもね、やっているときからも、終わった今も、ずっと心の奥でひっそりと、だけど確実な存在感をもって、残り続けている気持ちがあります。
それは、「ずっとやりたかった研究に取り組めていることが嬉しい」という研究ができることに対する喜び
私は、もう何年もこの分野の研究がしたくて、教員をやりながら大学院に進学しようかと検討していました。
最終的にはフィンランドに留学することになったけど、一番の根底にある思いは、この分野について学びたい、研究したいという強い気持ちでした。
辛かったのは本当です。
でも修論を通して、ようやくこの分野の一端を見せてもらえた気がして、ありがたいと思ったし、何よりうれしかった。
私はこうして修論に取り組めたことに本当に感謝しています。
その一方で、自分の修論の未熟さも痛いほど感じています。
もっとこうできたはず、こう書けたはず、って部分がたくさんありすぎて、修論の公開はやめておきました。
でも今、大学図書館で検索すると、自分の名前がタイトルとともに出ます。それが何より嬉しい
そして、修論としては提出したけど、今後もっとブラッシュアップできるところはしていくつもりです。
これからも、新しいチャレンジをしていきます。
でもまずは、修論を頑張ってよかった、この二年間が本当に有意義なものになってよかった、と心からの感謝をしています。
しばらくは、フィンランドの美しい夏を、ゆったりとした時間とともに過ごして、また活動再開します。
今後もぜひ応援してくださいね。
Kinaco 2025,7月 Finland

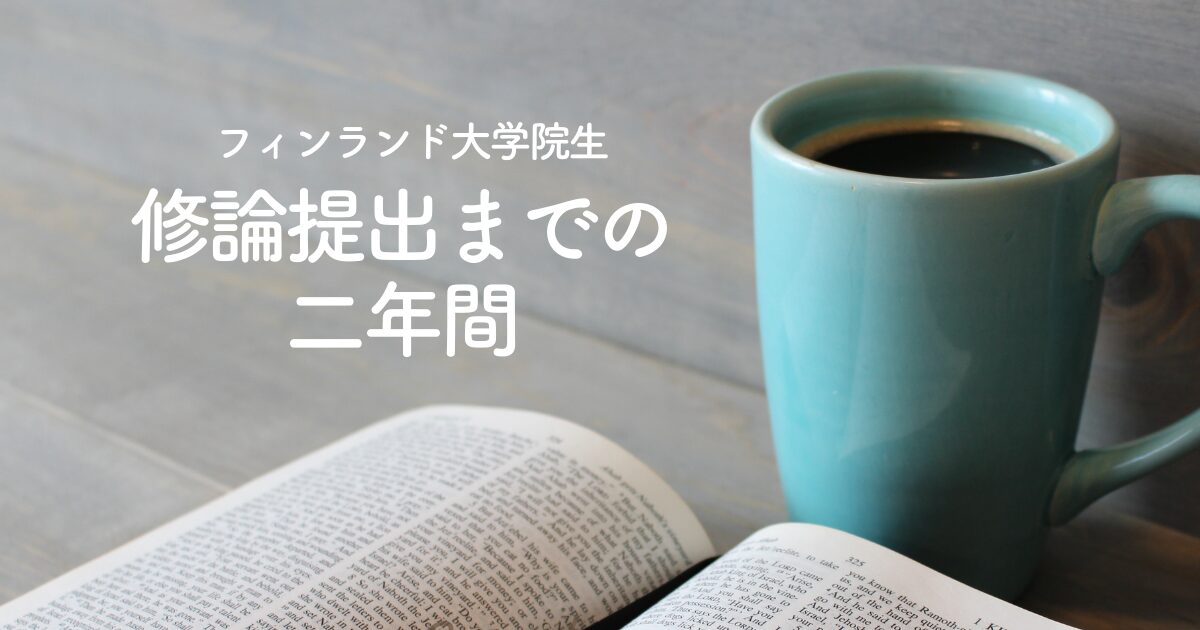
Comments